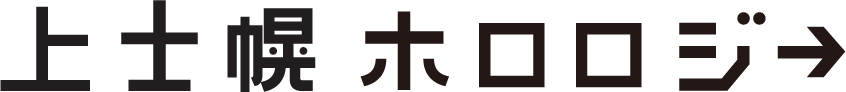少年時代の記憶を黒曜石に込めるものづくり。十勝工芸社・中編

上士幌市街地から国道273号線を糠平方面に向かって進んでいくと、白樺の木々に囲まれた白い建物が見えてきます。そこは「十勝工芸社」という工房で、黒曜石(十勝地方では十勝石とも呼ばれます)を加工し、石の魅力を引き出す工芸品を製作されています。今回はそんな十勝工芸社の店主 陶守統一さんのもとを訪ねたお話「その2」をお届けします。

WRITER
竹中 勇輔(たけなか ゆうすけ)
1994年生まれ。上士幌町出身。理学療法士。ホロロジーライターというチャンスを生かして会いたい人に会いに行きます。上士幌に帰ってきてけん玉にハマっています。よく聞かれますが町長と親族関係ではありません。
前編では「十勝工芸社」の陶守統一さんと工芸品の紹介、そして上士幌町で工房を開いた理由や製作についてのお話をまとめました。製作のお話では、エゾシカの角を利用して黒曜石を加工していることなどを伺い、とても興味深い内容でした。「その2」では黒曜石との出会い、弟子入り時代のこと、引き継いだ技術の伝達についてのお話をまとめました、ご覧ください。
黒曜石との出会い

次は黒曜石との出会いのお話を聞きたいです。どんなきっかけがあって、黒曜石に興味を持ったんですか?

最初に黒曜石に興味を持ったのは小学生の頃。私は足寄町の上利別というところで生まれたんですけど、家から学校まで20~30分くらいかけて歩いて通っていました。その通学路の両側は畑なんですが、雨が降るとその畑の中に、キラキラした黒曜石の鏃(やじり)が見えるんですよ。

黒曜石がそのままあったわけではなくて、鏃があったんですね。

これは何だろう?と興味を持って、それが鏃だということが分かってからは、どうやって作ったものなのかと興味が深まっていきました。

好奇心が広がったんですね。

実際に拾ったものを見せましょうか。(工房の方へ鏃を取りに行く)

私が見つけたものは縄文時代の石器なんですよ。


おぉ!

この石って、地中にあると水和層(すいわそう)という、電子顕微鏡で見ないとわからないような膜ができるんです。その膜の厚さを図ることで、石の年代がわかるんです。

木でいうと年輪みたいなものですか?

そうですね。それで昔は顕微鏡で膜の厚さを調べてたらしいんです。今は放射線で調べるから、かなり詳しい年代までわかるみたいですよ。

放射線で石の年代を調べる方法があるのは知りませんでした。

それで、こういう鏃が畑に落ちていて、雨が降るとキラキラ光るんです。拾ってからは、これをどうやって作ったのかということが気になって仕方がなくてね。

見ていて驚いたんですが、縄文時代のものがこの鋭さを保っているのがすごいですね。


すごいでしょう。これはきっと吹き矢かなにかだと思う。これを獲物に向かって吹いて、一つひとつ拾いに行くわけはないだろうから、柄は風化するけど、石は残ったんだね。狩猟に必要な道具だから、きっと大量に作って、それがあちこちに埋もれちゃったんだと思うんですよね。

へぇー。

話を戻しましょうか。あとは私の実家が商業をやっていたんだけど、林業の全盛期って、木をどんどん切り倒していくから、木がなくなっていくんです。そうすると人口も減少して経営状態が悪くなってね。そんなときに父が本別町で、黒曜石の加工をやってる人に出会って。それをきっかけに父は黒曜石の加工の仕事を始めたんです。

では、陶守さんが始める前にお父様が先にやられていたんですね。

そうなんです。父が始めたのは僕が中学生くらいのときでした。振り返れば、帰ってきては父の仕事を見たり、ちょっといたずらして加工したりしてたなぁ。石もいっぱいあるから、石器づくりに挑戦してみたりしましたね。

こどもの頃からものを作るという行為が好きだったんですね。

そうですね。とにかく手を動かすことが好きでした。

陶芸をやっていると、すごくその気持ちがわかります。

私は高校を卒業して神奈川県で勤めました。そのころは仕事が忙しくて石器作りどころではなかったですね。でも良かったこともあって、それは以前から興味のあった東京国立博物館に行けたこと。そこには北海道から産出された大きな石器が展示されていました。そこで再び興味が沸き起こっていくわけですよ。

石器への情熱が再燃したんですね。

そうそう(笑)。それを機に北海道に帰ってきて、黒曜石の仕事をやりたいと思い始めました。それで42歳のときに仕事を辞めて帰ってきたんですよ。

そういう経緯があったんですね。陶守さんが帰ってきたとき、お父様はまだ仕事をされていたんですか?

やっていたんだけど、体調を崩していてね。3年ぐらい一緒に仕事をしたあと亡くなりました。
弟子入り時代に学んだこと

お父様が亡くなられたのはとても辛かったと思いますが、3年間一緒に仕事をできたことは、陶守さんにとって宝のような時間だったのではないでしょうか?

そうですね、始めるのが何年か遅れていたら一緒に仕事ができなかったわけだからね。

お父様と仕事をしていた期間は、陶守さんにとっていわゆる弟子入りの期間だったと思いますが、一番勉強になったことは何かありますか?

石を磨く技術ですね。この石を見てください。石を磨いていく目の順番です。一番端が原石で、粗い目からどんどん細い目で磨いていきます。


荒い目はその辺りに落ちている黒曜石の質感と似ていますね。

落ちている石は河原で他の石とぶつかりながら転がるから、ザラザラしてますよね。そんな状態から粗い砥石から石を磨いていくんです。少しずつ砥石の目を変えていって、仕上げはフェルトで磨きます。これらの工程は黒曜石の加工の基本で、光沢の違いを使い分けて作品を作っていきます。

光沢の調整はかなり繊細な作業なんでしょうね。

黒って傷が目立つから、傷が残らないように磨くことは並大抵のことじゃないですね。父はおよそ40年の間で試行錯誤して、どんな順番で作業し、どのような道具を使うかを決めていきました。それは何十年もかかって生み出された磨き方、基本形なんです。

そんなに長い時間をかけて出来上がった技術なんですね。

私は突然帰ってきて、息子だからいろいろと教えてもらえましたが、そうでなければどうだったかわかりません。だから私は、その試行錯誤の時間がなかったおかげで、応用を考えるために時間が使えました。もし父がいなければ、磨く技術だけで20年以上かかっていたかもしれません。それが伝承できたのはラッキーでしたね。
引き継いだ技術の伝達について

陶守さんはお父さんの技術を引き継いだわけですが、陶守さんの元で勉強をしたいという方はいらっしゃいましたか?

石器作りは、累計だと300人以上に教えていました。高校生の修学旅行の体験や、社会科教諭の石器作りの研修会などでも教えましたね。上士幌町だと生涯学習センターでも3回ぐらい教えましたよ。でも教えるって大変ですよ(苦笑)。 黒曜石は石を割る工程が難しいから、私が全部破片を事前に作って準備しなければいけないんです。それでも体験中はバラバラになったり、手が切れちゃったりすることも多くて。

ガラスの破片と同じように鋭利だから、作業では危険も伴いますしね。

磨きを学びたいという人が来たこともありましたね。そのときは1週間その人につきっきりになってしまって、自分の仕事ができなくなったときもありました。技術を伝達するというのは非常に難しいなと感じていますよ。

陶守さんが今持っている技術を次の世代に引き継げないとなると、ここで失くなってしまうことになると思います。それについてはどんなふうに考えていらっしゃいますか?

できれば身内に引き継ぎたいと思っていました。でも息子は違う仕事をしていますし、娘も結婚しています。だから難しいかなと思ってます。

そうだったんですね。日本の伝統工芸も後継がいないければ衰退していくし、十勝でいうと農業も状況は似ている気がします。

そうですね。技術というのは1回失うと取り戻すのにかなりの時間と労力を要しますよ。

ある技術を持つ世代が次の世代に引き継ぐことができないと、またゼロに近いところからスタートになるということですよね。

うん、そういう悩みを持った職人さんはたくさんいると思います。今私は70歳だけど、父は72歳で亡くなったんです。でも亡くなる直前まで磨いていましたよ。そういうことを考えると、私もあと何年できるか分からないけど、やりたいことはいっぱいある。ただ時間が少ないこともわかっています。
いかがでしたでしょうか?実はまだまだお話は続くのです。最後となる後編は、私が個人的に一番聞きたかったことに迫ります。ものづくりに対する姿勢や考え方、アイデアの源泉など、何かを作っている人にとって勉強になるお話になるかと思います!ご覧ください。